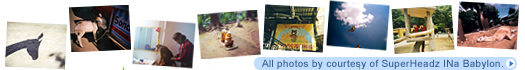2009年9月 9日
「『製作委員会』シンドローム -顕在化して来た、映画の著作権共有リスク-」
弁護士 福井健策 (骨董通り法律事務所 for the Arts)
今日、日本の商業的な劇場用映画はほとんどが「製作委員会」方式で製作されている。過去10年ほどで急速に拡大した、かなり日本特有な映画の製作方法で、TVアニメの製作でもしばしば見られる。
■製作委員会とは
「製作委員会」とは、基本的には複数の会社が資金を出資しあって映画を製作し、完成した映画の著作権を出資者が共有する方法である。「製作委員会」のほか、「●●パートナーズ」「●●プロジェクト」と名乗るケースもある。
しばしば「民法上の組合を組成する」という表現をとるが、組合は法人ではないので、関係者の共同事業のことをこう呼んでいるに過ぎない。「組合」や「委員会」という用語を使うか否かにかかわらず、複数の会社が映画を共同製作し著作権を共有して事業をおこなうならば、法律的には類似した扱いになろう。
本項では、こうした共同製作を広く「製作委員会方式」と呼ぶことにする。
2001年にスタジオジブリの『千と千尋の神隠し』が、ジブリ・日本テレビ・電通・徳間書店・ブエナビスタジャパン・東北新社・三菱商事の7社共同製作で作られた際には多いと感じたものだが、最近では、10社以上が参加する製作委員会など当然の感がある。
「キネマ旬報」を参考に、2008年に劇場公開された邦画のうち、東宝・東映・松竹・日活・角川配給で製作会社の数を判別できた77作品についてみれば、一本あたりの平均製作者数は8.4社(東宝・東映・松竹配給に絞れば9.3社)にも達する。一社単独で製作された映画は『釣りバカ日誌』など2作品に過ぎない。TV局が中心となって製作された映画に系列の地方局が加わるケースでは、30社以上に及ぶ。仮に頭割りすれば、一社ごとの著作権持分は実に3%だ。
■不況化で目立って来た、共有著作権をめぐるトラブル
こうした映画の製作委員会をめぐって、昨年後半から目立って増えたのが、委員会メンバーの一社が倒産しそうだとか、「経営不振で身売りした」「利用窓口を勝手にどこかに委ねた」といったトラブル例である。映画ビジネスはそもそも浮き沈みが激しい上に不況のあおりを受け、中小の委員会メンバーの経営が行き詰るシナリオが多いようだ。
製作委員会の一員が経営危機に陥ると、もちろん他のメンバーへの支払が焦げ付くといった心配もある。しかし、それに劣らず危惧されるのは、作品の利用が害されることだろう。
著作権の原則をいえば、権利が共有であれば、共有者全員の同意がないと作品は利用できない。原則通りで行けば、一社でも正常な判断ができない状態に陥ると、作品の利用が中断する危険が生じるのである。
また、著作権持分の流出リスクもある。著作権法には、他の共有者の同意がないと共有持分を第三者に譲渡できないという規定がある。しかし、強制執行のように任意でない持分の移転には、共有者の同意は必要ない。これまた著作権法通りなら、一社が経営不振に陥って他の債権者から強制執行をかけられると、作品の共有持分は未知の第三者の手にわたるかもしれないのだ。
こうした危惧から、他のメンバーは作品の保全やサルベージ(救済)に心を砕くことになる。
もっとも、以上は今回の不況に限った事態ではなく、「多数の出資者が著作権を共有する」というスキーム自体が持つ多様な課題の一角に過ぎないとも言える。
映画の著作権の保護期間は「公表から70年」である(欧米など更に長い例もある)。10社が著作権を共有するとしよう。70年はおろか10年も経つうちには、10社のうち1社くらいは、倒産しないまでも経営がまったく様変わりしていても不思議はない。新規ビジネスをめぐってメンバー同士の思惑が対立する事態など、容易に起きるだろう。
何らかの事情で作品の利用について共有者のコンセンサスが得られなくなれば、同じ問題が生ずる。
無論、多くの作品では不測の事態に備えて詳細な「製作委員会契約」を交わし、万全を期している。にもかかわらず、筆者の経験を言うならば、これまで「全員にとって万全な契約」というものは目にしたことがない。契約とは本来、当事者の妥協の産物だからである。
たとえば、利用の安定性だけに注目するならば、「放送利用はX社がその裁量で一切を取り決め、ビデオグラム化はY社がその裁量で一切を取り仕切る」と明瞭に利用権者が決まっている契約がベターだ。しかし、過去にDVDやネット配信が生まれたように、これから誕生するであろう無数の新規利用も含めて、全ての扱いを契約で取り決めておくのは土台無理である。
しばしば見られるのは、その対極に位置する「●●利用については当事者の協議で決する」という条文だ。協議のうえ多数決で決まると明記している例も多いが、明記がなくてもそう考えていいのか。民法の「組合契約」の節と著作権法の条文をにらんで頭をひねることになる。
また、契約の有効期間が比較的短いものは、仮に利用についての詳細な条文があったとしても、契約期間が終わればそうした規定じたいが原則として失効する。その際に、著作権の帰属をどうするか特に取り決めなければ、おそらく全員一致でないと作品は利用できないという状態に戻る。
今後、映画の二次利用がより多様化しロングテール化するならば、こうした契約や利用をめぐる協議は各社の利益に直結する。日本的な「合意優先」の話し合いがいつも可能とは限らず、交渉はより複雑化・長期化しよう。
しかも、改正された金融商品取引法(金商法)の規制を受けないためには、今後の製作委員会では出資者全員の関与がいっそう求められるとも言われ、意思決定を特定の会社に一任する扱いのハードルは上がる。
■日本特有の方式
諸外国でも、国際共同製作のケースをはじめ、数社が映画著作権を共有する例は少なからず存在する。しかし、日本ほど多数の会社による著作権共有が常態化した国は異色だろう。
また、良く知られたことだが、ハリウッドの会社はあらゆる権利を一社で保有することにこだわる。例外として著名なのは1997年製作の「タイタニック」で、史上最高額にふくらんだ製作費を捻出するために20世紀フォックスがパラマウントに出資を仰ぎ、見返りに米国内での配給権を同社に与えたケース。こうした取り決めを「スプリットライツ」というが、フォックスの当時の会長はインタビューに答えて、「もうスプリットライツはやらない」と発言したとされる。
米国では映画業界に限らず、作品の権利が分散してコントロールできなくなることへの抵抗感は強い。それがしばしば、「オールライツ」一元管理へのこだわりとなって表れる。
なぜ、日本ではこれほど製作委員会方式(=多数出資者による著作権共有)が広まったのだろうか。
共同製作が増えた背景には、製作費の高額化への対応、多数で出資することによる事業リスクの分散、そして放送局・出版社・広告代理店など多業種が力をあわせることによるシナジー(相乗)効果への期待がある。出資をおこない損失リスクを負う以上、各社が映画の特定の利用の窓口になったり、収益から分配を受けたいと思うのは当然だ。
更には、映像プロダクションの権利をめぐる闘争もこれに絡んだ。プロダクション側には歴史的に、映画を制作しても資金提供者側に全部の権利が渡ってしまい、作品の二次利用収入からの分配を一切受けられないという不満があった。そこで、収益分配を受けるために、作品に一部出資して、製作委員会のメンバーになろうという動きが相次いだのである。
こうした動機はいずれも理解できる。しかし、それは「出資をして利用窓口になったり収益の分配を受ける」動機に過ぎない。なぜ「著作権の共有」なのだろうか。
レコード業界に「共同原盤」という言葉がある。複数の会社がCDなどの音楽原盤を共同で製作する形態をいう。「共同原盤」という言葉から、音楽原盤に発生する著作隣接権(いわゆる原盤権)も常に共有だと誤解されることがあるが、しばしば著作隣接権は一社が単独で保有している。この場合の「共同原盤」とは、本質的には複数の会社が収益分配を受けることしか意味しないのである。
このように、「収益分配を受けること」と「著作権を共有すること」の間には、少なくとも必然的な連関はない。
あるいは映画界で起きていることは、「収益分配を受けるためには出資しなければならず、出資する以上は著作権を共有する」という直線的な思考が招いた、特殊な事態なのかもしれない。
■映画資産の長期活用のために
リスクを減らしつつ必要な資金を集め、シナジー効果を発揮する上で、共同出資はメリットの多い方法だ。短期間で映画を幅広く展開し、短期間で資金を回収するには好適なモデルといえる。
しかし、著作権共有に限っていえば、長期にわたって映画を活用し、映像資産化して行くには、どうにも課題も多い。現行の法制度を前提にするならば、現在の「みんなで共有、なんでも協議」の時代に作られた作品たちは、そう遠くない将来、次々と権利をめぐる死蔵の危機に直面する可能性さえある。
「映画の著作物の著作権は・・・映画製作者に帰属する」という規定(第29条)をおき、映画監督らスタッフから著作権を「取り上げて」まで権利の一元管理を目指したのが、1970年制定の現行著作権法であった。結局大勢での著作権共有がスタンダードになるならば、それは著作権の原始退行と言えなくもない。
当の映画監督協会は、90年代初頭にはすでに、「リスクを分散させようとして出資者を多様化させ、著作権の共有をすすめれば、安定を欠くことになるのは必然」(文化庁での同協会意見)と警鐘を鳴らしている。
しかし、共同製作による権利共有の問題点は、その後必ずしも幅広くは議論されて来なかった。むしろ、今年に入り、ジャパン・デジタル・コンテンツ(JDC)信託の業務停止に象徴されるような「映画ファンド」不振を受けて、大手映画会社は製作委員会方式への傾斜をますます強めている、とも報道される。
最近のハリウッド映画の質の評価は、ひとまず措く。少なくとも米国では、黄金時代の幾多の映像資産はいまだにメジャー会社の重要な収入源であり、それが業界の体力を下支えしている。権利が一元管理されている映像資産は、ネット配信などの新規ビジネスにも対応がきく。また、それゆえに各社はハイビジョンリマスターなど、映像資産の市場価値にみがきをかける努力を怠らない。
日本は、共同出資のメリットを生かしつつ、権利分散化のリスクを回避するモデルを見出すことができるのか。
無論、一本の映画ごとに特定目的会社(SPC)を設立するなど、以前から提案されている方策は幾つかあり、すでに実行されてもいる。次回は、こうした試みをはじめ、著作権共有の負の側面=「製作委員会症候群」への対処策を考えてみたい。
以上
■ 弁護士 福井健策のコラム一覧
■ 関連記事
「DAOってなんだお。
ファン・コミュニティや資金調達の新たな仕組み」
2024年3月27日 弁護士
岡本健太郎(骨董通り法律事務所 for the Arts)
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。