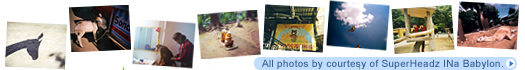2012年1月25日
「TPPが特許に与える影響~特に医療・医薬品を中心に」
弁護士 諏訪公一(骨董通り法律事務所 for the Arts)
2011年11月12日、野田内閣総理大臣がホノルルAPEC首脳会合においてTPP(環太平洋戦略的経済提携協定)の交渉参加を表明して以来、TPPの各論点についてはさまざまな観点から議論がなされているところです。TPPにおける米国政府による知的財産の要求項目のうち、著作権に関する問題点は、福井健策によるInternet Watch内のコラム「TPPで日本の著作権は米国化するのか ~保護期間延長、非親告罪化、法定損害賠償」と同続編のQ&Aをご覧頂き、今回のコラムは、その他の知的財産とTPP、とりわけ医療・医薬品の特許に関する議論を中心に、ポイントを絞って、内容を簡単にご説明いたします。
なお、本コラムは、米NGOより公開された「TPPにおける米国政府の知財要求項目」(以下、「知財要求項目」という。PDFはこちらのページから)を基に記述をしております。また、国境なき医師団「どのようにTPPは医薬品アクセスに脅威を与えるか」(以下、「MSF意見書」という。PDF(英文)はこちら)をも参考にしております。
■医療方法の特許性について
知財要求項目では、人間または動物の手術方法、治療方法、診断方法に関する発明に、特許性を認めなければならないとしております(知財要求項目8. 2条(b))。
現在、日本の特許法の審査基準においては、人間が対象に含まれないことが明らかであれば、動物の手術方法・治療方法・診断方法については、特許の対象となるとされております。しかしながら、人体の存在を必須の要件とするもの、具体的には、人間を手術する方法、人間を治療する方法、人間を診断する方法に関する発明は、「産業上の利用可能性」(特許法29条1項柱書)がないとして、特許を受けることができません(特許庁審査基準第Ⅱ部1. 2. 1)。ただし、医療機器、医薬それ自体、医療材料の製造・処理方法(細胞の調製、加工による製品・製剤化)、医療機器の作動方法は、特許の対象になります。
なお、諸外国においては、アメリカは手術方法、治療方法、診断方法ともに特許の対象となるとし、欧州においては、手術方法、治療方法、診断方法の一部は特許の対象になりません(諸外国の法制については、平成20年11月25日付け特許庁「我が国と各国の特許制度比較~医療分野~」(PDFはこちら)(知的財産戦略本部 先端医療特許検討委員会資料))。
日本で医療方法の特許性が認められていなかったのは、従来、医学研究を営利目的の開発競争に巻き込ませるべきではないという政策的理由、人の生存や尊厳にかかわる人道上の理由などにより、特許による独占を認めるべきではないと考えられているためです。特に、医療方法に特許を認めると、緊急の患者が病院に運び込まれてきたときに、治療を行う医師が特許権者に許諾を得なければ命が助からないという状況が発生しうるのではないかと言われています。
この懸念への対処としては、医療方法に特許を認めた上で、医師の行為について例外を設けるという方法もあります。たとえば、医療方法に特許が認められているアメリカにおいても、医師が侵害に該当する医療行為を行った場合には、その医師や医療行為に関与する関連医療機関には差止請求や損害賠償請求ができないと規定されております(米国特許法287条c )。
なお、ここでいう「医療行為」には、装置、製造物または組成物に関する特許の使用、組成物の使用に関する特許の実施、バイオテクノロジー特許の実施が含まれませんので、全ての医師等による医療行為が除外されるわけではなく、また、医師等が行う医療行為でない場合には特許権者の許諾が必要となります。
医療方法に関する特許を認めるかどうかにつき、特許を認めることによるインセンティブによる開発の促進、大学の医療技術に対する投資回収、重複研究の回避などを考えると、医療方法に特許を与えることにも一理あるように思います。また、現状の文言上は、「産業上利用することができる」とのみ規定されており、人体を必須の構成要素としない発明、たとえばiPS細胞などの研究に関する発明は特許となりうるにもかかわらず、人体に関する部分だけを殊更「産業上の利用可能性がない」として、特許として認めないことは一貫していないと考えられます。一方で、医療行為に対する萎縮効果の他、欧州は医療方法特許がないにもかかわらず国際競争力があること、医師や研究者のインセンティブは特許制度を使わずとも守れるものではないか、医療費の高騰の可能性などの懸念の声があるのも確かです。なお、2009年5月29日付け知的財産戦略本部 知的財産による競争力強化専門調査会 先端医療特許検討委員会報告書「先端医療分野における特許保護の在り方について」(PDFはこちら)においても、医療方法に特許性がないという基本方針は維持されています。
いずれにせよ、仮に、知財要求項目のとおり医療方法に特許を認める方向となった場合においても、医療現場に混乱を与えるようなものではあってはなりません。医療方法に特許性を認めるとしても、権利制限規定を設けると共に、現場にいる医療関係者の実態を把握し、その権利制限規定が実際の医療にあたって問題が発生しないよう適切な内容となっているかを検討することが必要です。
■特許期間の延長の可能性の有無
著作権と同様、TPPにより特許の期間が延長されるかのような議論もみられます。しかしながら、知財要求項目のうち、著作権は著作者の死後70年への延長要求が明記されているものの(知財要求項目4. 5条)、特許には期間に関して言及する記述はありません。アメリカにおいては、著作権の保護期間の原則は著作者の死後70年となっておりますが(アメリカ著作権法302条)、特許法については、日本と同じく出願から20年です(アメリカ特許法154条(a) (2) )。そのことから、特許について、TRIPs協定33条で保護すべきと定められている20年という期間を大幅に超えて各国に特許期間の延長を要求することは、現時点では想定されていないように思われます。
■有効成分が公知な医薬の特許性
知財要求項目8. 1条において、既知の物を使用した新しい構造、使用又は方法について、たとえその発見が、その物について既に知られた効能を促進するものでなくても、特許性を認めるよう要求しております。もし、この規定を導入した場合は、古い医薬品の新しい使用や、物の効能に大きな効果を与えないような新構造であっても特許性を認めることになり、実質的に同じものを特許で再度保護するものではないかという批判もあります。しかし、用途発明(ある物の未知の属性を発見し、この属性により、そのものが新たな用途への使用に適することを見出したことに基づく発明)に関していえば、有効成分が公知であっても医薬用途が新規であるものについては、現在の日本の運用でも、特許要件である新規性が認められております(特許審査基準第Ⅶ部2. 2. 1. 1 (3) )。たとえば、抗菌剤の有効成分として知られている化合物Aにつき、「化合物Aを有効成分とするアルツハイマー病治療薬」との発明には、拒絶理由がないとされています。したがって、物の発明(用途発明)に関して言えば、大きな影響はないかもしれません。
知財要求項目8. 1条の規定の記載は必ずしも明確ではありませんが、現在も、そしてこれからも、医薬品業界においてある物質が、本来特許が切れている用途等であるにもかかわらず永遠に特許の対象となるような状況を防ぐために(MSF意見書では、「evergreen」と表現されています)、その用途変更等が当業者にとって容易であるかどうかを特許庁が慎重に判断しているかを監視することが必要です。
■臨床実験データの排他的独占権
特許の議論とは少し離れますが、臨床実験データの排他的独占権についての議論があります。ジェネリック医薬品の審査においては、現在、臨床試験は不要です。これは、ジェネリック医薬品は、新薬の臨床使用経験を踏まえたものであるからです。この臨床実験データについては、莫大な投資が行われているため、特許の有効期間とは別の議論として、臨床実験データの独占権を与える動きがあります(MSF意見書によれば、アメリカの機関(Pharmaceutical Research and Manufacturers of America(PhRMA))が、臨床実験データの排他的独占権を強く主張しているようです)。アメリカにおいては、臨床実験データに関して、排他的独占権が認められております。
現状の日本はどうでしょうか。現在、「臨床実験データの排他的独占権」という権利はありません。しかしながら、日本では、薬事法上の医薬品の再審査期間が結果として医薬品の試験データを保護する期間として機能しております(薬事法14条の4)。ここで、医薬品の再審査制度とは、新薬について、承認後一定期間(原則8年。薬食発第0401001号)が経過した後に、企業が実際に医療機関で使用されたデータを集め、承認された効能効果・安全性について、再度確認する制度です。この再審査期間中に承認申請される後発医薬品は、新医薬品と同等の申請資料が必要とされております。つまり、ジェネリック医薬品を再審査期間中に承認申請をしようとするならば、新医薬品と同等の申請資料、つまり承認申請の臨床実験データを集めるために自ら治験(3~7年かかります)を行わなければならず、「低価格の医薬品」であるジェネリック医薬品として発売することはできなくなります。そのため、再審査期間が終了するまでは、特許有効期間満了後すぐにジェネリック医薬品を発売することを目的として承認申請することもできず、さらに言えば、特許有効期間が満了していたとしても承認申請が実質的にできないことになります。このように、再審査期間は結果として新医薬品の臨床実験データを保護する期間となっております(平成18年6月8日付け知的財産戦略本部「知的財産推進計画2006」47頁参照)。結果として、ジェネリック医薬品を発売するためには、その特許が切れていることの他、再審査期間が経過していることが必要になります。
現状を前提に、TPP加入により、日本にも、「臨床実験データ独占権」を設置するよう求められるでしょうか。知財要求項目9. 2条によれば、医薬製品に関するデータの保護に関する条項が、知財要求項目9. 3条によれば、医薬製品の特許との関係に関する条項が挿入される旨の規定がありますが、現時点で詳細な内容については記載されておりません。しかしながら、それがどのような内容になるかの参考として、米韓FTAがあります(米通商代表部HPによる米韓FTA条項はこちら)。そして、知財要求項目9. 2条に相当する米韓FTA 18. 9条1項および18. 9条2項では、実験データの独占権(data exclusivity)について、以前承認されたことがあるか否かなどの場合を分けて、化学物質等の製品の医療データまたは証拠について、一定の範囲・期間で、データ等提出者の事前の同意なく使用できないとしています。そのうち、一例を挙げると、新医薬品(医薬品使用としてその国で以前承諾を受けた化学物質を含んでいない製品)の市販承認の条件として、国が、その新医薬品の開発者が相当の労力をかけて作成した安全性・効率性に関するデータ等の提出をさせた場合またはデータ等の提出を許可した場合には、少なくとも市販承認から5年間は、データ提出者の事前の承諾なく、その新医薬品のデータ等に基づく同種の製品(すなわち、後発医薬品)を販売させてはならない旨の規定を定めています(米韓FTA 18. 9条1(a) )。
米韓FTAの規定では現状の日本のような「事実上のデータ保護」は不十分であり、アメリカのような「独占権」という形の「権利」を求められる可能性もあります。しかしながら、米韓FTAの文言それ自体は、「権利を付与せよ」という条項ではなく、「他人に対してデータ使用を許可しない」という規定方法であるので、私見では、現状の日本の再審査期間のような規定でも問題はないと考えられます。なお、仮に再審査期間という制度による事実上の独占ではなく、「独占権」を与える必要があると判断されるならば、特許とは別の新しい独占権を創出する必要があります。この場合、データに積極的な権利を付与することから、その権利の内容、範囲等について、予想外に広範囲な権利が付与され、後発医薬品の承認が遅れる事態にならないよう、注意しなければなりません。
■新規性喪失の期間(グレース・ピリオド)について
先願主義の下では、新規性の判断基準は、「出願前」を基準として判断します(特許法29条)。ただし、それをそのまま適用すると、大学教授が学会などで発表するにより新規性が喪失する結果、学会での発表や博覧会の出品等に抑制的になる可能性があります。その弊害を取り除く必要があるため、一定の期間に限り、例外を認める条項を定めております。この期間を「グレース・ピリオド」と呼びますが、知財要求項目8. 8条(b)では、発明の公表から特許出願するまでに認められるグレース・ピリオドの期間を12ヶ月とすることを要求しています。
日本では、グレース・ピリオドに関する規定は特許法30条に定められておりますが、同条は、平成23年改正が行われております(平成24年4月1日から施行)。グレース・ピリオドの内容の前に、平成23年改正の説明をいたしますと、改正前30条では、特許を受ける権利を有する者が、試験、刊行物発表、特許庁長官指定の学術団体による研究集会での文書発表などの限定列挙された場合に新規性が喪失された場合において、6ヶ月以内に出願をした場合には、その開示では新規性は喪失しないとされていました。しかし、平成23年改正により、グレース・ピリオドの対象範囲については限定列挙をはずし、「特許を受ける権利を有するものの行為に起因」したものと網羅的にすべて対象とし、6ヶ月以内に出願をした場合には新規性を喪失しないとされました(なお、米国においても、2011年9月の特許法改正により、グレース・ピリオドの規定である102条(b) が改正されました。改正法では、基本的に同一者の同一発明による開示や公表には1年の猶予期間があるとされております)。このように、日本ではグレース・ピリオドが6ヶ月であるため、仮に知財要求項目に沿う形とするならば、その期間が12ヶ月に延長される可能性があります。
グレース・ピリオドの延長は、発明者の行為に起因したものまたは意に反して公知となったものであれば、その発明者にとっては「新規性を喪失せずに出願ができる期間が長くなる」ことを意味するため、より発明者に有利となります。また、アメリカとグレース・ピリオドが同一になることで、アメリカとの産学連携がしやすくなるという意見もあります。一方で、延長により特許の見通しが現状よりさらに不明確になることからビジネスに混乱を与える可能性があるという意見もあり、12ヶ月という期間延長が妥当か、慎重に検討しなければなりません。
■まとめ
冒頭に紹介したMSF意見書は、日本においてTPPに加入することに対する危機への警鐘を鳴らしたものではなく、あくまでTPPに加入することにより、日本を含め、知的財産、特に医薬品に関する特許を必要以上に保護するあまり、途上国における安価な医薬品へのアクセスの促進が阻害される可能性があることに警鐘を鳴らすものです。この意味で、同じ知的財産権の分野であっても、直接、TPP加入により日本の制度をドラスティックに変えようと試みる著作権とは異なる視点を与えてくれるものです。現状、特許に限定していえば、そして、(現時点では全容は明らかではありませんが)日本で導入することだけを考えれば、著作権ほど現状からドラスティックな変更がなされる可能性は少ないと考えられます。しかし、逆にいえば、特許に関し、日本がTPPに加入する必要性があるのか、という疑問もあります。特許はあくまでも知的財産項目の中の一つです。特許権者と活用のバランスが崩れないように注意しながら、その他の知的財産項目、ひいてはその他の交渉項目との兼ね合いも考えて、日本および環太平洋の経済圏にとって何が最善かを考えて交渉していく必要があります。
以上
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。