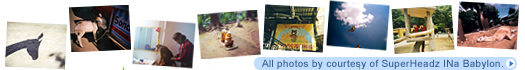2013年4月26日
「実演家の権利について再確認してみよう-北京条約を契機に 【前編】」
弁護士 唐津真美(骨董通り法律事務所 for the Arts)
2012年6月に、WIPO(世界知的所有権機関)の加盟国が参加する視聴覚実演の保護に関する外交会議が北京で開催され、「視聴覚実演に関する北京条約」(Beijing Treaty on Audiovisual Performances)(以下本稿において「北京条約」)が採択されました。これは、すでに条約によって保護されている歌手などの"音の実演家"と同様に、俳優や舞踊家といった"視聴覚的な実演家"(・・って何だ?という話はまた後で)について、著作隣接権を設定するなどしてその保護を図ることを目的とした条約です。
今回のコラムでは、北京条約の解説を中心に書きたいと思いますが、「視聴覚実演」に関する規定は、日本の著作権法の中でも特にわかりにくいと言われる部分です。そこで、まずは、現行著作権法が定めている実演家の権利について全体像をながめてから、北京条約の内容や意義について見ていきたいと思います。実演家の権利についての解説だけで結構な分量になってしまったので、前編・後編に分けてお届けします。
なお、「解説なんていいから早く条約の中身が知りたい!」という方は、文化庁が公表している条約の原文と参考訳[PDF:257KB] をご覧ください。
■ 実演家の権利をめぐる国際条約の歴史-北京条約の位置づけ
著作権法は、条約によって国際的な調和がよく図られている法律の一つと言えるでしょう。実演家の権利についても条約によってその保護が図られ、国内法の規定は条約と歩調を合わせるように改正を重ねてきました。
今回採択された北京条約はWIPO加盟国によって採択されたものですが、このWIPOは、1967年に署名された「世界知的所有権機関を設立する条約」(「WIPO設立条約」)が1970年に発効して設立されたものです。1974年に国際連合の専門機関の一つとなり、工業財産権・著作権・著作隣接権の国際的保護と関連する条約や協定を管理しています。
WIPOの設立前である1961年には、実演家・レコード製作者・放送事業者の保護を目的として、「実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約」がローマで作成されていました。(いわゆる「実演家保護条約=ローマ条約」。日本は1989年に加盟。)
WIPO設立後間もない1971年には、ユネスコとWIPOにより、海賊版レコードの防止を目的として「許諾を得ないレコード複製からのレコード製作者の保護に関する条約」(「レコード保護条約」)が作成されました。(日本は1978年に加盟。)
その後1996年には、一般的に「WIPO実演・レコード条約」として知られる「実演及びレコードに関する世界知的所有権機関条約」(WPPT)が採択されました。この条約は、実演家人格権の設定や、実演家・レコード製作者の複製権・譲渡権・貸与権・利用可能化権の設定を主な内容にしています。日本は、著作権法に実演家の人格権に関する規定を設けるなど、法改正をした上で、2002年に正式にWPPTに加盟しました。
WPPTでは、主にレコードに固定された実演の保護が図られており、視聴覚的実演における実演家の権利は対象に含まれていませんでした。2000年にはジュネーブにおいて、視聴覚的実演の保護条約に関する外交会議が開催されたのですが、この時は、映画産業の強い意向をバックにしたアメリカの反対により、条約の採択には至りませんでした。(もっとも、全部で20条ある条約の草案のうち、権利行使に関する条項を除いた19の条項については、暫定合意に達しました。)
このような、実演家の権利をめぐる長年の国際的取り組みを経た後に、今まで国際的に十分な保護が図られてこなかった視聴覚実演家の権利保護についてようやく採択されたのが、今回の北京条約なのです。
(なお、知的財産権を巡る国際的なルール作りのための協定として、GATT(関税及び貿易に関する一般協定)ウルグアイ・ラウンド交渉の結果、1995年にWTO(世界貿易機関)の設立協定が発効し、付属書の一つとして「知的所有権の貿易関連の側面に関する協定」(「TRIPs協定」)が締結されました。TRIPs協定の中にも、実演家・レコード製作者・放送事業者の保護に関する規定がありますが、本コラムでは割愛します。)
北京条約の締約国は、他の締約国の実演家に対して、条約に規定される保護を与えなければならず(北京条約第3条)、また自国の法制に従い、条約の適用を確保するために必要な措置を定めることが求められています(同第20条)。したがって、日本が条約を締結するにあたっては、国内法である著作権法との整合性を確認する必要があります。ところが、実演家の権利に関する部分の規定は、度重なる法改正の影響もあって、著作権法の中で特に難解な構造になっています。そこで、この【前編】では、まず現行の著作権法が実演家の権利についてどのように定めているか、概要を解説したいと思います。
■ 「実演」「実演家」ってなんだっけ?
楽曲や脚本といった著作物を例に考えてみると、これらの著作物が多くの人に届くためには、歌手・演奏家・俳優のように、「演じる」ことによって著作物を受け手に伝達する人が重要な役割を果たしていることに気づきます。また、同じ楽曲でも、別の歌手が歌うとまったく違うイメージになることもあるように、「演じる」という行為が、単なる伝達ではなく、創作的な側面を持つ場合もあります。この「演じる行為」が実演であり、「演じる人」が実演家です。
著作物を伝達するという意味で重要な役割を果たすのは、実演家に限りません。著作権法は、著作物の創作者ではないものの、著作物の伝達に重要な役割を果たすものとして、「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」「有線放送事業者」に著作権に準じた権利(著作隣接権)を与えて、その保護を図っています。実演家の権利は、実演家の著作隣接権として規定されているのです。
著作権法上、著作隣接権で保護される「実演」とは、「著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、またその他の方法により演ずること」と定義されています(著作権法(以下「法」)第2条1項3号)。また著作物を演じていない場合でも、芸能的な性質を有するもの(手品など)はこれに含まれると規定されています。また、「実演家」については、「俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出する者をいう」と定義されています(法第2条1項4号)。一般的に「実演家」と聞くと、前半の「実演を行う者」が頭に浮かぶと思いますが、指揮者や演出家も実演家と規定されているのは意外かもしれません。また、実演家は、プロである必要はありません。学校の演劇祭で演じる生徒も、趣味で演奏している一般人も、著作権法上は立派な「実演家」です。(なお、映画などの監督はその役割が舞台演出家と似ている点もありますが、映画監督は、「実演家」ではなく映画の著作物の「著作者」になります。)
■ 「実演家」の権利に関する著作権法の規定
» 実演家人格権
上で述べたように、実演には創作的要素もあります。この点を反映して、実演家には、著作者人格権と同様の「実演家人格権」が与えられています。権利の一つは、実演が公衆に提供または提示されるときに、その氏名を実演家名として表示するか、またどのような表示をするか決めることができる権利、いわゆる「氏名表示権」です(法第90条の2)。もう一つの権利は、自己の名誉または声望を害する実演の改変を無断で行われないという、「同一性保持権」です(法第90条の3)。著作者人格権と似ていますが、たとえば、著作者人格権における同一性保持権では著作者は、「その意に反して著作物の変更、切除その他の改変を受けない権利」を持っており、「意思に反しない」という主観的な要件が含まれるのに対して、実演家人格権の場合は「意に反していても名誉・声望を害さない改変ならば良い」という意味で実演家人格権の方が狭くなっています。
なお、実演家人格権も著作者人格権と同様に一身専属的なものであり(法第101条の2)、実演家の死亡によって消滅するのですが、これまた著作者人格権と同様に、たとえ実演家の死後であっても、実演を公衆に提供する者は、実演家が生きていれば人格権侵害に相当したような行為をしてはいけないという規定がありますので、留意が必要です(法第101条の3)。
» 著作隣接権
実演家の権利のうち、実務で問題になることがより多いのは「著作隣接権」です。すでに述べたように、著作権法上、著作隣接権は、「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」「有線放送事業者」に与えられており、それぞれ内容が異なります。実演家に与えられている権利の概要は以下のとおりです。
録音権・録画権(法第91条):実演家の許諾なしに実演を録音・録画されない権利です。著作権者の複製権に相当する権利ですが、一度実演家の許諾を得て録音・録画された実演については、権利が及ばないという重要な制約(いわゆる「ワンチャンス主義」があります。ワンチャンス主義については次項でもう一度説明します。
放送・有線放送権(法第92条):実演家の許諾なしに実演をテレビ・ラジオで放送・有線放送されない権利です。実演家の許諾を得て録音・録画された実演を放送・有線放送する場合には権利が及ばないなど、一定の制約があります。ですから音楽CDなど「商業用レコード」は実演家の許可がなくても放送・有線放送できるのですが、このような商業用レコードを利用して放送・有線放送する場合には、実演家は、放送事業者から二次使用料を受領することができます(法第95条)。
送信可能化権(法第92条の2):コンサートや、演劇の舞台などにおける実演をインターネット配信するような場合、実演家には、無許諾でアップロードされない権利(送信可能化権)が認められています。ここでも、実演家の許諾を得て「録画」された実演などについては権利が及ばない(=実演家の許諾はなくてもアップロードできる)のですが、他方、「録音」された実演については、実演家の権利が残ります。したがって、音楽CDをアップロードする場合には、実演家の送信可能化権が問題になることになります。(このあたりの規定が非常に分かりにくいのですが・・・)
譲渡権(法第95条の2):実演家の許諾なしに実演を録音物・録画物の譲渡によって公衆に提供されない権利です。ここでも、実演家の許諾を得て「録画」された実演などには権利が及ばない(=実演家の許諾はなくても譲渡できる)のですが、他方、映像音楽など以外の「録音」された実演については、実演家の譲渡権は残ります。したがって、音楽CDを譲渡する場合には、実演家の譲渡権が問題になることになります。なお、譲渡権は最初の譲渡の時に行使されると以後は行使できないので、例えば、購入したCDを転売する場合には、譲渡権は問題になりません。
商業用レコードの貸与権(法第95条の3):実演家は、商業用レコードを無許諾で貸与されないという権利を持っています。この権利は商業用レコードの発売後1年が経過すると消滅し、その後、貸レコード業者(この言葉自体が既に何となくレトロですが)に対する報酬請求権に変わります。
■ "視聴覚的な実演家"の権利について
» ワンチャンス主義
実演家の著作隣接権について今まで読んできた方は、実演家の許諾を得て録音・録画された実演については、実演家の権利が制限されていることに気づいたと思います。これが、いわゆるワンチャンス主義のあらわれなのです。実演家の重要な役割に照らし、実演家に著作隣接権を与えて保護をはかる意義がある一方で、特に映画のように多数の実演家が関連する作品については、出演した実演家全員に対して長期間にわたって許諾権を与えてしまうと、許諾が得られないために結局その映画の利用が実際上不可能になるという事態が容易に想像されます。このような事態は、作品を受け取る側だけではなく、実演家自身も望むところではないでしょう。そこで、著作権法上、実演家の権利(実演の利用を許諾する権利)については、対象となる実演が最初に利用される時だけ認めるといういわゆる「ワンチャンス主義」が認められているのです。
ワンチャンス主義が端的に表れている例として、「映画の著作物」に録音・録画された実演については、その映画の著作物がさらに録音・録画されることについて、実演家の録音・録画権、放送権、譲渡権等が及びません(法第91条2項、第92条2項2号ほか)。例えば、俳優が映画に出演する場合には、当然、その俳優から録音・録画権の許諾を受けて俳優の実演(演技)が録音・録画されているので、その後その映画をDVDにする場合には、あらためて出演した俳優の許諾を得る必要がないことになります。
» テレビ番組への出演-局内制作or局外制作で差が?
著作権法上「映画の著作物」とは劇場公開される映画だけを意味するわけではありません。「映画の著作物」にはテレビ映画、ビデオソフト等も含まれます。
では、通常のテレビ番組についてはどうでしょうか。テレビ番組は、ライブでない限りは一度収録(録音・録画)され、編集を経たうえで放送されています。では映画の場合と同様に、出演者による録音・録画権の許諾に基づいて収録したと言えるかと言うと、そうとも限らないのです。放送事業者には、出演者から録音・録画の許諾を得なくても、「自己の放送のために」実演を一時的に録音・録画できる権利が認められており(法第44条)、さらに放送の許諾には、契約で特に定めない限り録音・録画の許諾を含まないという規定もあるからです(法第63条・第103条)。テレビ放送の収録については、出演者から録音・録画の許諾を得て録音・録画されたのか(ワンチャンス主義が働く場面なのか)、放送の許諾のみを得て収録されたと考えるのか、両方の可能性があることになります。放送の許諾のみしかない場合は、ワンチャンス主義が適用されませんので、そのテレビ番組をDVD化する場合には、あらためて出演者(実演家)の許諾を得ることが必要ということになります。
この点については、現在も見解が統一されているとは言えない状況ですが、テレビ業界では、「局内制作番組についてはワンチャンス主義が適用されない可能性があるが、局外制作番組についてはワンチャンス主義が適用される」というケースが多いようです(もちろん例外もあります)。局内制作番組の収録は、放送事業者であるテレビ局が「自己の放送のために」録音・録画したと言えますが、局外制作番組については、録音・録画するのは放送事業者ではないので、出演者から録音・録画の許諾を得て録音・録画したことになる、という解釈のようです。(権利関係の処理は重要な問題なので、そんな微妙な解釈に頼らずに、出演者と毎回きちんと契約書を交わせば安心・確実なのに、筆者は思うのですが。)
例外規定が入り組んで複雑な、著作権法上の実演家の権利について見てきました。さて、【後編】では、現行著作権法の内容に照らしながら、いよいよ北京条約の中身に入って行きたいと思います。
(【後編】につづく)
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。