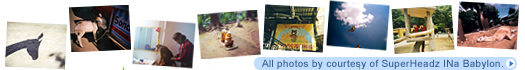2015年8月12日
「Basketball Law(バスケットボール法)入門
~バスケットボール選手の国際移籍を例に~」
弁護士 小林利明 (骨董通り法律事務所 for the Arts)
今回のコラムのテーマはスポーツです。最近のスポーツ関連の話題といえば、新国立競技場の建設に関する問題や、東京オリンピックのロゴが別のロゴとそっくりだと騒動になった話題などがあります。ロゴ騒動については、商標法や著作権法の観点から法的な分析もされていますが(詳しくは唐津弁護士によるこちらの記事もご参照ください)、スポーツイベントのロゴのみならず、スポーツ選手の肖像権やパブリシティ権を含む広い意味での知的財産権は、国際化するスポーツビジネスを巡る法律問題の1つとして重要です。しかし、同様に重要であるにもかかわらず、選手の国際移籍に潜む法的リスクについてはあまり検討が行われていません。そこで本コラムでは、バスケットボールを題材に、米国で発達しつつあるバスケットボール法がどんなトピックをカバーしているのか概観した後、バスケットボールの国際化の現状に触れ、最後に、バスケットボール選手の国際移籍に潜む法的リスクを紹介して、「バスケットボール法入門」とさせていただきたいと思います。
1. Basketball Law(バスケットボール法)がカバーするトピックの広さ
日本にはBasketball Lawという名前の法律があるわけではありませんが、それは直訳すると「バスケットボール法」であり、バスケットボールに関する法律問題を扱うスポーツ法の一分野ということができます。バスケットボールというスポーツ特有の問題もあれば、スポーツ全般に共通する問題を、実際にバスケットボールの世界で問題となった事案を通じて検討する場合もあります。
バスケットボール法などというと、何を勝手にそんなジャンルを設けているのだ、というお叱りを受けそうですが、この名称を考えたのはもちろん私ではありません。たとえば、全米規模の法律家団体であるAmerican Bar Association(米国法曹協会)からは、The Little Book of Basketball Lawという本も2013年に出版されています。この本は、バスケットボールに関してアメリカで実際におきた事件・訴訟を取り上げて紹介する書籍ですが、そこでカバーされている論点は多岐にわたります。観戦中の観客の怪我や選手のドーピング、スポーツ中継と著作権の問題、ドラフトされた選手に選手会とリーグとの間の労働協約が適用されるか、セクハラなどの労働法の問題、リーグコミッショナーの制裁権限の範囲といった問題まで、非常に興味深い論点が数多く取り上げられています。さすがは訴訟大国アメリカ、よくもまあバスケットボールに関する事案だけで1冊の本になるほど裁判が起きているなぁ、と驚きを隠せません。
アメリカでは最近もバスケットボールに関連した興味深い訴訟が多く起きています。少しだけご紹介しましょう。
まず、今、最も旬な(?)話題であるロゴ問題に関してですが、本年(2015年)1月に、元NBAのスーパースターであるマイケル・ジョーダンのAir Jordanブランドのロゴ(Jumpmanロゴ)を巡る著作権侵害訴訟が起きています。この訴訟は、ロゴの原型は自分が撮影しナイキに貸与した写真だと主張する写真家が、Jumpmanロゴを付したAir Jordanブランドでスポーツウェア・シューズ等を製造販売するナイキを著作権侵害で訴えたという事件でしたが、米国連邦地裁は、原告の写真のうちの創作性ある部分とJumpmanロゴの間には実質的類似性がないという理由で、本年6月にナイキを勝訴させました(現在、控訴されています)。Air Jordanブランドが全世界的に大人気ブランドとなっていることを踏まえると仮にナイキが敗訴していたならば膨大な額の損害賠償額が認められた可能性もある事件でした。ちなみに、Air Jordanのロゴを巡っては、マイケル・ジョーダンがAir Jordanロゴを無断使用していた中国企業を相手取り商標権侵害訴訟を中国で提起したものの、上訴審レベルで敗訴したという報道が先月なされています。このように、知的財産を巡る紛争は、スポーツビジネスとは切っても切れない関係にあります。
スポーツビジネスを巡る紛争は知的財産を巡るものだけではありません。本年3月には、昨シーズン40年ぶりにリーグ優勝を果たしたGolden State Warriorsの観戦チケットに関する訴訟が起きています。そこでは、アメリカ大手チケットリセール業者であるStubHubが、「チームはシーズンチケットホルダーに対して、その保有するチケットを売る場合には特定のチケット転売業者を利用して売るように指示していた」などと主張して、独占禁止法違反でチームなどを訴えており、裁判は現在も継続中です。
2014年に、ロサンゼルスを本拠地とするLos Angeles Clippersの長年のオーナーが、プライベートな空間で行った人種差別発言がマスコミにリークされたことをきっかけとしてチームの売却を余儀なくされた事件もありました。オーナーは、リーグや選手会からの圧力によりチームを強制的に売却させられたなどと主張して分厚い訴状とともに訴訟を提起し、現在も裁判は続いています。このようなことが起きると、影響はチーム内だけにとどまりません。本件がメディアで報道された数日後には、チームのほぼ全てのスポンサーがスポンサー契約を解除しましたが、そもそも契約解除が可能か、可能だとしてもすでにスタジアム内にある広告等をどうするかといった問題も生じます。私も事件直後にClippersのホームスタジアムに試合を観に行きましたが、スポンサー広告が一切なくなったスタジアム内は異様な雰囲気でした。同チームの選手らは、抗議のために試合をボイコットすることも検討したようですが、これには選手会とリーグとの間の労働協約の解釈も影響したはずです。会場外ではデモも行われ、警察が出動し厳戒態勢が敷かれていました。このように、本件は、たとえプライベートな空間での一言であっても、単なる一個人の「不祥事」としては片づけられないことを示す一例といえるでしょう(余談ですが、本件の対応にあたったNBAコミッショナー、Adam Silverはニューヨークの法律事務所の訴訟弁護士としてキャリアをスタートさせた弁護士です)。
アメリカほどではないものの、日本でもスポーツに関しては様々な紛争が起きています。いくつか挙げれば、プロ野球観戦中に観客がファールボールに当たり怪我をした場合の球団の法的責任が争われた事案(札幌地裁平成27年3月26日判決(平24(ワ)1570号))や、サッカーの中田英寿選手の自伝を巡り「引用」の成否やパブリシティ権が争われた知的財産訴訟(東京地裁平成12年2月29日判決(平10(ワ)5887号))、プロバスケットボールチーム運営をめぐるリーグとの間の紛争(東京地裁平成23年12月2日判決(平21(ワ)44138号事件))、球団合併をめぐりプロ野球選手会が労働組合にあたるかが争点となった裁判(東京高等裁判所平成16年9月8日判決(平16(ラ)1479号事件))などがあります。
以上のとおり、スポーツを巡る紛争類型は様々であり、バスケットボール法はそのいずれをもカバーします。しかし、アメリカとは訴訟文化等が大きく異なる日本においては、裁判を含む公表ベースで争われたバスケットボール関連事案は極めて限られています(スポーツ紛争全体についても、近時増えてはいるものの、決して多くありません)。もちろん、紛争の数が多いこと自体は歓迎すべきことではないでしょう。しかし、事例の積み重ねが少ないと、実際の事例を通じた将来のルール形成という効果は期待できません。そして何よりも、もし狭い部分社会の中で旧態依然とした理不尽な「力関係」がまかり通っているがゆえに紛争の「暗数」が多いだけだとしたら、スポーツ文化の発展のために、変えていかなければならないでしょう。
2. バスケットボールの国際化
バスケットボール選手の国際移籍について検討する前に、まず、バスケットボールの国際化の現状を見てみましょう。
(1) NBAの国際化
リーグ・選手の国際化は、プロスポーツにとっては今や欠かせず、これは全世界的な傾向です。サッカーや野球はいうまでもなく、バスケットボールについてもそうです。 例として、世界最高峰のバスケットボールリーグであるNBAの状況を見てみましょう。NBAの調べによれば、1991年当時の外国出身選手は合計で21人だったそうです。その当時はアフリカ系選手(コンゴ出身のDikembe Mutomboやナイジェリア出身のHakeem Olajuwonなど)や一部のヨーロッパ系選手(いずれもクロアチア出身のDrazen PetrovicやToni Kukocなど)が中心でしたが、特に1992年のバルセロナオリンピック以降、NBAのグローバル化が積極的に進められました。その後徐々に外国出身選手は増え、昨シーズンは、NBAの開幕ロスター登録選手450人のうち、外国出身選手は101人(出身国は37か国)もの人数となり、これはNBA歴代最多だそうです。米国外出身者としてNBA入りし、不動のエース、あるいはリーグの顔となった選手も少なくありません。ドイツ出身のDirk Nowitzkiや中国出身のYao Ming、オーストラリア出身のKyrie Irvingなどはその好例でしょう。また、アメリカ人ではありますが、台湾系2世のJeremy Linは2012年に一大センセーションを巻き起こし一躍リーグの顔となりました。
そして今年は、またNBAに新たな風が吹き込まれました。昨シーズンは初のインド人NBA選手が誕生し、本年6月25日に行われたNBAドラフトでは、初めてインド人選手が指名されています。また、今月初旬には、NBA発の試みとして、アフリカ出身の現役NBA選手対チーム・アメリカということで、南アフリカ共和国においてエクシビションゲームが開催されました。これはますます海外進出を狙うNBAにとって、中国に続き、インドやアフリカへとビジネスを海外展開させるための大きな足掛かりです。
(2) 日本バスケットボールの国際化
日本のリーグでも外国籍選手は多く活躍しており、bjリーグでは、MVPその他の受賞者の大半は外国籍選手となっています。そのため、むしろ、外国籍選手の出場時間を制限するために、同時にコート上でプレイできる人数に制限を設けるなどの措置がとられています。
では日本人選手は海外で活躍しているのでしょうか。実は、数は少ないながら、日本人(日系人)選手が海外でプレイした実績は案外古くからあります。1947年には、NCAA(アメリカにおけるいわゆるインカレ)優勝経験もある日系2世アメリカ人の三阪亙がNBA(ニューヨーク・ニックス)でプレイしています。三阪は史上初の非白人NBA選手でした。このことはあまり知られていませんが、同じ1947年にはアメリカ・メジャーリーグで初の黒人選手と言われるジャッキー・ロビンソンが試合に初出場したことも考慮すれば、単にバスケットボールという枠を超えて、歴史的にも非常に意味のある出来事です。
最も知名度の高い日本人NBAプレイヤーといえば田臥勇太でしょう。彼はドラフトの対象とはならなかったものの、2004年にはフェニックス・サンズと契約しNBAで4試合に出場しています(その他にも、日本人男子選手では1981年に岡山恭崇がNBAのドラフト指名を受けていますが、プレイはしていません。)
近時NBAにチャレンジしている日本人選手といえば、昨シーズンNBA傘下のD-leagueに参戦した富樫勇樹がいます。彼は日本のスポーツメディアでも取り上げられ、テレビCMにも起用されましたので、ご存じの方もいるかもしれません。しかしバスケットボールはNBAだけではありません。筆者が個人的にも応援している安藤誓哉は、カナダのプロリーグを経て本年6月にはフィリピンリーグでも活躍し、現在はロサンゼルスで行われている独立系リーグであるDrew Leagueにおいて、現役トップクラスのNBA選手とともに経験を積んでいます。
また、忘れてはいけないのが女子バスケです。米国最高峰の女子プロリーグであるWNBAでは、1997年には荻原美樹子、2008年には大神雄子がプレイしています。今年は渡嘉敷来夢がWNBA入りし大活躍しています。実は国際バスケットボール連盟(FIBA)のランキングでは男子は47位であるのに対して、女子は15位であり、日本女子の実力はなかなかなのです。
さらに、大学レベルでいえば、日本代表選手にも選出されている渡邊雄太は現在George Washington大学でプレイしており、またヒル理奈は現在ルイジアナ州立大学でプレイし、昨年はNCAAでベスト16入りも果たしています(同大学は、元NBAのスーパースターであるシャキール・オニールの出身校でもある名門校です)。
残念ながら野球やサッカーとは違いあまりメディアで取り上げられることはありませんが、このように、日本人選手も着々と海外に出て行って修行を積んでいます。
3. バスケ選手の国際移籍の手続
(1) 国際移籍の手続
さて、上述のようなプロバスケ選手の国際移籍はどのような手続きを経て行われているのでしょうか。 選手の国際移籍にあたっては世界共通のルールが設けられており、それを管轄する組織がFIBAです。FIBAの規約は内容により大きく4つの"Book"に分けられますが、選手の国際移籍に関する規制は、Book 3の第2章に定められています。第2章は、国際移籍に関するすべての判断を行う権限はFIBAにあることを定め(37条)、FIBAの定める規則は原則としてすべてのFIBA会員連盟に適用されます(40条)。たとえば日本ではJBA(日本バスケットボール協会、会長は川淵三郎)が、アメリカではUSA BASKETBALLがFIBA会員連盟であり、2015年3月現在でFIBAには215か国の連盟が加盟しています。
海外チームに移籍するといっても、選手個人が海外の移籍先を見つけることは通常容易ではありません。そこで、積極的に海外移籍を希望する選手は、後述するエージェントに依頼して移籍先を探してもらうのが一般的です。そのために選手とエージェントとの間でもエージェント契約が締結されます。ただ、晴れて自分に興味のある移籍先チームが見つかったとしても、移籍先のチームとの間で条件面を交渉し、選手契約を締結する必要があります。移籍先候補との契約交渉は通常エージェントが行いますが、選手本人もその内容を把握している必要があることは当然です。さらに、選手契約に合意しても、移籍先チームでプレイするためには、現所属先連盟からのletter of clearance(許可状)を取得することが必要となり、許可状がない国際移籍は無効とされます(99条)。日本選手が海外でプレイする場合を例にとると、選手は、日本バスケットボール協会が発行する許可状を取得し移籍先に提出するよう求められます(42条)。この許可状は、日本のクラブとの間での選手契約関係などがないことを証明するためのものであり、これを取得することにより、当該選手は海外でプレイすることが可能になります(73条)。各国連盟は、他国チームへの移籍予定日時点において自国クラブとの契約が残っていることを理由とする場合以外には、許可状の発行を拒否することはできません(46条)。上記が国際移籍のルールの大枠となりますが、この他にも、二重国籍者の扱い、後述する最低年齢制限など、細かなルールが実にたくさん設けられています。
(2) FIBAエージェント
このような手続に関するコミュニケーションは一般に英語で行われ、また、移籍先チームとの選手契約交渉も含めれば必ずしも簡単な手続きではありません。また、FIBAルール(当然ながらすべて英文です)を読み、その内容を理解するだけでも一苦労です。そのため、選手個人ですべてをマネージするには負担が多いといえるでしょう。そこで、FIBAでは、選手又はクラブがFIBAに登録したエージェントを利用することを認めています(132条以下)。
FIBAエージェントになるためには、年に2回スイスで行われる他、不定期にアメリカ又はオセアニア地区で開催される試験(択一式筆記試験と面接)に合格し、登録費用を納める必要があります。登録会費は本稿執筆時の為替レートで年間約13万円とかなり高い金額ですので、気軽には登録できません。しかし、それでもエージェントの質にはかなりばらつきもあるようで、特に海外のエージェントの話を鵜呑みにすると、いつの間にかFIBAルールに違反しかねないので、要注意です。筆者がある選手をサポートしたときの経験でも、そのような例がありました。
※ ちなみに、サッカー界においては、エージェントの一定の質を保ち、選手の国際移籍におけるトラブルを減らすという目的で、エージェントの登録制をとっていました。しかし、エージェント登録をめぐる不正や国外移籍の約7割がライセンスを持たない者により行われていたという実態を踏まえ、本年4月以降は登録制度を廃止したそうです(Number Web「Jリーグ観察記」参照)。
(3) 手続違反の効果
日本では、スポーツ選手の国際移籍についてエージェントとして、あるいはエージェントのアドバイザーとして助言を行う法曹資格者が少ないように思われます。
多くの選手がエージェントに期待する主要な業務は、選手としての価値を上げ、よりよい待遇の契約やスポンサーを探すことです(映画「Jerry Maguire」(邦題:「ザ・エージェント」)で主演のトム・クルーズ扮するスポーツエージェントが、依頼者たるアメフト選手から繰り返し求められていた業務です)。そのため、契約書の記載や手続の確認のために割く時間は後回しになってしまうということもあるのかもしれません。
しかし、プロアスリートとして活動するからには、契約内容の理解をおろそかにして、後になって「そんなはずではなかった」ではすまされません。特に自国の常識が通用しない海外移籍にあっては、極力トラブルを減らすための準備を怠らないようにすべきでしょう。
国際移籍に関するFIBAルールに違反すると様々なペナルティが課されます。そして、ルールに違反したために移籍先でプレイできないという事態も実際に発生しています。ある事案では、中国出身の選手が日本の実業団でプレイするにあたり日本国籍を取得したところ、18歳未満の移籍を原則禁止するFIBAルール(50条)に違反したとして、実業団での選手登録の抹消を余儀なくされました。このときは、FIBAは移籍補償金の支払いを条件に翌年度の選手登録は認めたものの、紆余曲折を経て東京地裁での裁判となり、仮処分決定を得てやっと選手登録が認められることになりました(ニッカンスポーツ・コム参照)。しかし、プロスポーツ選手が自身のトップレベルでプレイできる期間は非常に短いのですから、このような事情で1シーズンでもプレイができなくなってしまうことは大きなダメージとなりかねません。
同様のことは、日本選手が海外でプレイする場合についても起こりえます。選手の中には、プレイに集中したいとの思いから、国内での自分の選手契約の内容についてさえよく把握できていない場合も少なくないそうです。ましてや国際移籍となると、さらに高度な理解と経験が求められます。エージェントはまさにそのような場合に存在するわけですが、基本的な法的事項を理解した上でクライアントに適切な助言ができているかは、そのエージェント次第と言わざるを得ません。
4. さいごに
日本のバスケットボール界も、川淵会長の強力なリーダーシップにより、FIBAから下されていた国際試合出場停止処分を予想以上の短期間で解除することに成功しました。今後は東京オリンピックを控え、バスケットボールのみならず、スポーツそれ自体や関連ビジネスがますます盛んになっていくことが予想されます。バスケットボール男子・女子日本代表は2020年のオリンピックに出場できるでしょうか。日本人NBA選手やWNBA選手はそれまでにあと何人誕生するでしょうか。世界各国からどのような代表選手が日本にやってくるのでしょうか。そもそも新たなスタジアムをいくらの予算でオリンピックまでに完成させるのかという点も気にはなるところですが、その点はさて措くとしても、オリンピックに向けてのスポーツ界の動向が今から楽しみでなりません。
以上
■ 弁護士 小林利明のコラム一覧
法的若しくは専門的なアドバイスを目的とするものではありません。
※文章内容には適宜訂正や追加がおこなわれることがあります。